
真夏の夜の夢へ突っ走る
— 20年東京五輪立候補 —
先週のこのコラムに「日本の若者は確実に育っている — 仲間と力を合わせて世界と闘う五輪戦士 — 」のタイトルで<真夏の夜の夢ではない。ロンドンから吹いてきた涼やかな風に、いましばらく身を委ねていたい>と書かせていただいた。その通り、いまも私はロンドンからの風の中にいるようだ。
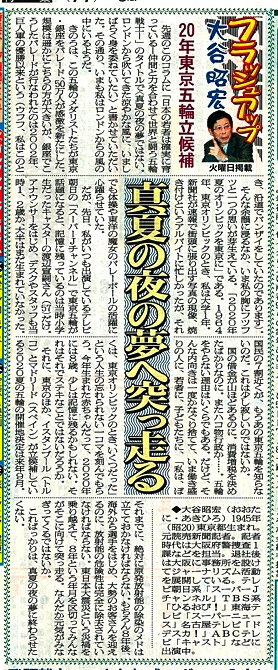
きのうは、この五輪のメダリストたちが東京・銀座をパレード、50万人が感激を新たにした。規模は遥かにこちらの方が大きいが、銀座でこうしたパレードが行なわれたのは2002年、巨人軍の優勝以来という(ウフフ、私はこのとき、沿道でバンザイをしていたのであります)。
そんな余韻に浸るなか、いま私の胸にフツフツと一つの思いが芽生えている。「2020年夏のオリンピックを東京に」である。1964年、東京オリンピックのとき、私は大学1年。新聞社が速報で街頭に張り出す写真の現像、焼き付けというアルバイトに忙しかったが、それでも体操や東洋の魔女のバレーボールの活躍に心躍らせていた。
だが、先日、私がいつも出演しているテレビ朝日の「スーパーJチャンネル」で東京五輪が話題になると、記憶に残っているのは当時小学生だったキャスターの渡辺宣嗣さん(57)だけ。アナウンサーをはじめ、デスクやスタッフも当時1、2歳か、大半はまだ生まれていなかった。国民の7割近くが、もうあの東京五輪を知らないのだ。これは少し寂しいのではないか。
国の借金が山ほどあるのに。消費増税を決めたばかりなのに。またハコ物行政か……。五輪をやらない理由はいくらでもある。だけど、そんな内向きは一度かなぐり捨てて、いま働き盛りの人に、若者に、子どもたちに、「私は、ぼくは、東京オリンピックのとき、いくつだった」という人生の忘れられない一コマを刻んでもらう。今年生まれた赤ちゃんだって、2020年には8歳。少しは記憶に残るかもしれない。それはそれでステキなことではないだろうか。
それに、東京のほか、イスタンブール(トルコ)とマドリード(スペイン)が立候補している2020夏の五輪の開催地決定は来年9月。それまでに、絶対に原発放射能の除染のメドは立てておかなければならない。もちろん8年後、海外から選手をはじめ、大勢のお客さんを迎えるのに、放射能の危険性は完全に除去されていなければならない。東日本大震災という災禍を乗り越えて、8年という年月を区切ってみんながそこに向けて突っ走る。なんだか元気がみなぎってくるではないか。
こればっかりは、真夏の夜の夢に終わらせたくない。
(日刊スポーツ・西日本エリア版「フラッシュアップ」2012年8月21日掲載)
|