
できることを、できるときに
− 震災ボランティアに思うこと −
大型連休のまん中。熊本、大分に大勢のボランティアが入っているという。このたびの震災では、そのボランティアの入る時期や災害時のテレビ番組の自粛をめぐってさまざまな意見が私たち報道する側にも寄せられた。だけど、簡単に答えの出るものではない。できることを、できるときに─それでいいんじゃないのかな。
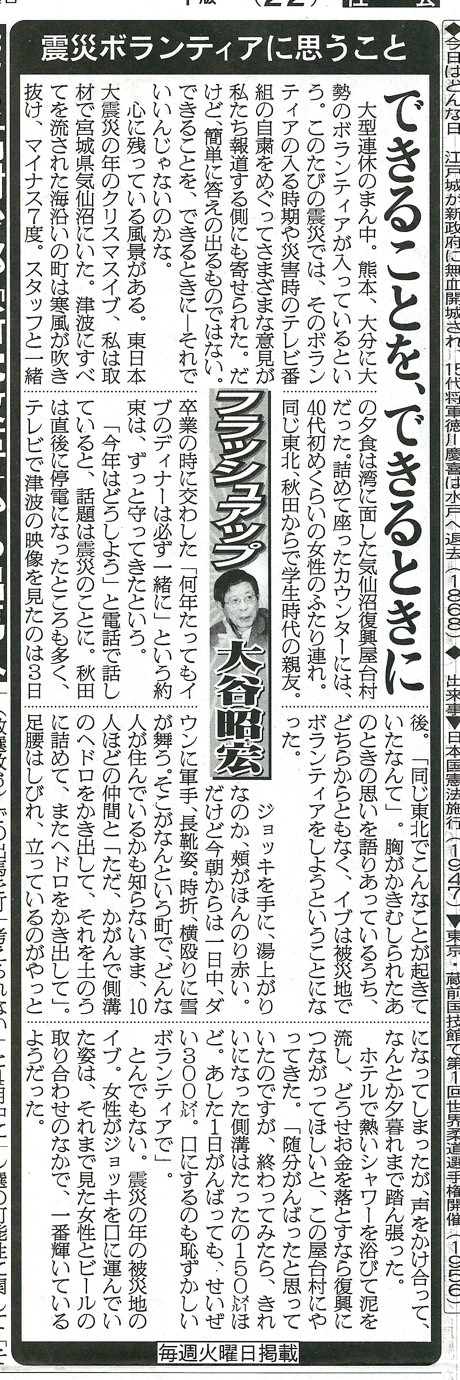
心に残っている風景がある。東日本大震災の年のクリスマスイブ、私は取材で宮城県気仙沼にいた。津波にすべてを流された海沿いの町は寒風が吹き抜け、マイナス7度。スタッフと一緒の夕食は湾に面した気仙沼復興屋台村だった。詰めて座ったカウンターには、40代初めくらいの女性のふたり連れ。同じ東北、秋田からで学生時代の親友。卒業の時に交わした「何年たってもイブのディナーは必ず一緒に」という約束は、ずっと守ってきたという。
「今年はどうしよう」と電話で話していると、話題は震災のことに。秋田は直後に停電になったところも多く、テレビで津波の映像を見たのは3日後。「同じ東北でこんなことが起きていたなんて」。胸がかきむしられたあのときの思いを語りあっているうち、どちらからともなく、イブは被災地でボランティアをしようということになった。
ジョッキを手に、湯上がりなのか、頬がほんのり赤い。だけど今朝からは一日中、ダウンに軍手、長靴姿。時折、横殴りに雪が舞う。そこがなんという町で、どんな人が住んでいるかも知らないまま、10人ほどの仲間と「ただ、かがんで側溝のヘドロをかき出して、それを土のうに詰めて、またヘドロをかき出して」。足腰はしびれ、立っているのがやっとになってしまったが、声をかけ合って、なんとか夕暮れまで踏ん張った。
ホテルで熱いシャワーを浴びて泥を流し、どうせお金を落とすなら復興につながってほしいと、この屋台村にやってきた。「随分がんばったと思っていたのですが、終わってみたら、きれいになった側溝はたったの150メートルほど。あした1日がんばっても、せいぜい300メートル。口にするのも恥ずかしいボランティアで」。
とんでもない。震災の年の被災地のイブ。女性がジョッキを口に運んでいた姿は、それまで見た女性とビールの取り合わせのなかで、一番輝いているようだった。
(日刊スポーツ「フラッシュアップ」2016年5月3日掲載)
|